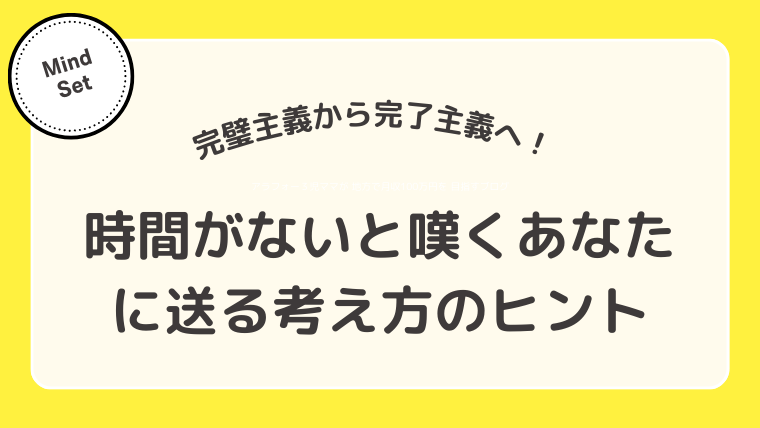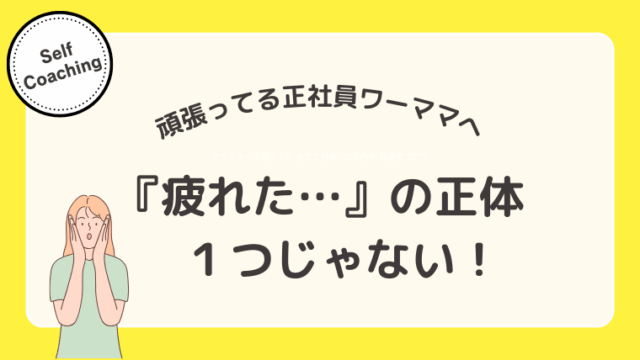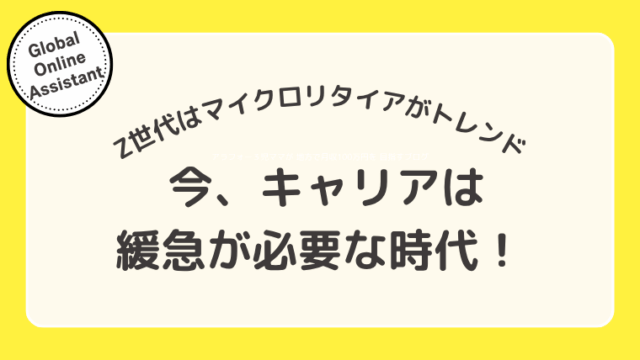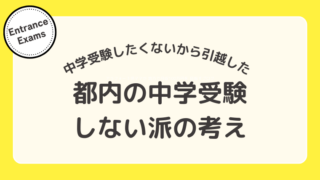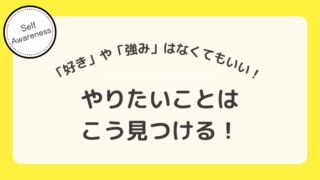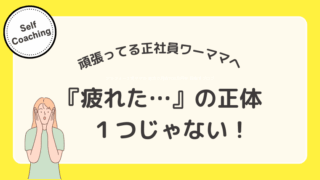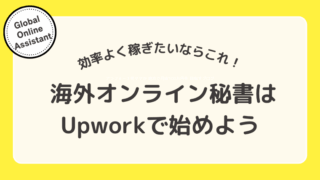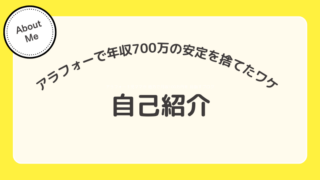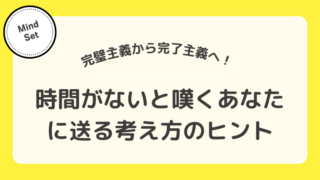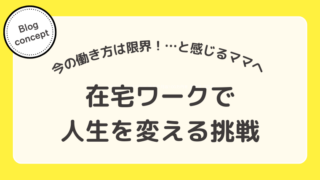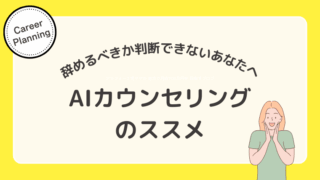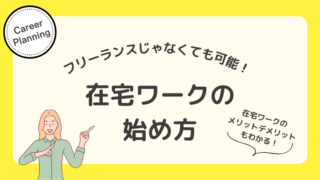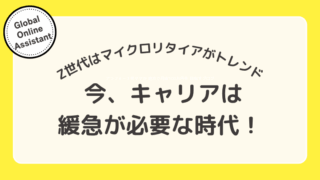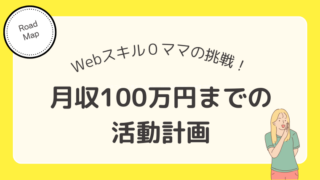あなたはいつも『時間がない』と口にしていませんか? もしくは、
『やることが多すぎて時間が足りない』とお悩みではありませんか?
毎日ダラダラ過ごしているわけではない、
むしろ一生懸命頑張っている。
それなのになぜか時間がない…
そんなあなたは、もしかしたら
『完璧主義』
『こだわりが強い』
といったタイプかもしれません。
今回の記事では、そんな完璧主義タイプのあなたが今必要な”時間を生み出す”方法を、
『完了主義』になることで実現する。そんなお話をしていきます。
そんなのこれまで何度もトライしてみたよ〜
分かっていてもなかなか抜け出せないんですよね〜
でも、だからこそ今回ご紹介する数々の研究結果や事例を知れば、あなたはきっと完璧主義から完了主義に切り替えたいと今まで以上に強く思うはず!
初めの方の完璧主義や完了主義の解説を飛ばして、研究内容や事例紹介など、気になる部分だけをお読みいただいても構いません。
ただ、最後まで読んでいただければ、完了主義に切り替えられる具体的な考え方や実践方法がわかり、日々のゆとりも成果も手に入ります!
ぜひ『時間がない!』から抜け出せる自分をイメージしながらお読みください。
それでは行ってみましょう!
完璧主義の特徴
 完璧主義とは「常に完璧を求めてしまう思考や行動のクセ」のこと。そういう人は、自分に厳しかったり、成果よりも完璧さにこだわってしまうという性質があります。
完璧主義とは「常に完璧を求めてしまう思考や行動のクセ」のこと。そういう人は、自分に厳しかったり、成果よりも完璧さにこだわってしまうという性質があります。
ではあなたはどのくらい完璧主義でしょうか。
下の10項目で当てはまるものが多ければ多いほど、完璧主義傾向が強いと言えます。
1. 100点じゃないと提出できない
→ 完成度が不十分だと感じると、納期を延ばしたくなることがある。
2. ミスを「許せない」と思ってしまう
→ 自分の小さなミスでも何度も思い返して落ち込んでしまう。
3. 「すごいね」と言われないと自分の価値がないように思う
→ 他人からの評価で自分の存在意義を測りがち。
4. 他人に任せるより、自分でやったほうが早くて確実と思ってしまう
→ 結果として、自分の手が空かない。
5. 「まぁいっか」と割り切るのが苦手
→ 妥協=悪いこと、手を抜いた気がして落ち着かない。
6. 「失敗したくない」といつも心の中で思っている
→ 新しいことに挑戦するハードルが高い。
7. 目標を達成しても「まだまだ」と自分を褒められない
→ 常にもっと上を目指してしまう。
8. 他人にも高い基準を求めてしまう
→ 仕事のパートナーやチームに対してイライラしてしまう。
9. SNSで他人の完璧な投稿を見ると落ち込む
→ 「なんで自分はできてないんだろう」と比較してしまう。
10. すべてのタスクを完璧にこなそうとして、時間がいくらあっても足りない
→ 時間内に終わらずにいつもモヤモヤ。自己嫌悪に陥りがち。
完璧主義のメリット・デメリット
先ほどのチェックリストの例示は完璧主義の負の側面を表したものでしたが、実はそれらの特徴は、頑張り屋で責任感が強いという強みの裏返しでもあるんですよね。
そんな表裏一体の完璧主義。メリットとデメリットを整理してみました。
メリット
| 向上心が高い | 常に「もっと良くしたい」と考えるので成長できる。 |
|---|---|
| クオリティにこだわる | 細部まで丁寧に仕上げるので、完成度が高くなる。 |
| 責任感が強い | 自分の仕事に対して真剣に向き合う姿勢がある。 |
| 信頼されやすい | 丁寧・正確・抜けが少ないため、周囲からの信頼が厚い。 |
| 問題点に気づきやすい | 小さなミスや違和感にも敏感で、トラブルの予防につながる。 |
デメリット
| 時間がかかる | 納得できるまでやろうとして、タスクに時間がかかる。 |
|---|---|
| 行動できなくなる | 「失敗したらどうしよう」と思い、行動にブレーキがかかる。 |
| 人に頼ることが苦手 | 多くのタスクを自分一人で抱えてしまうので、時間不足に陥りがち。 |
| 自分にも他人にも 厳しくなる |
自分を否定しがちだし、自分の基準を他人にも求めてしまい、人間関係にストレスが生まれる。 |
| 途中で挫折しがち | 自分の思い通りにいかない場合、納得がいかず続ける気を無くしてしまうことも。 |
つまり、完璧主義はうまく付き合えば自分の信頼感を支える”強み”となり、
逆にこだわりすぎると自分を苦しめる”凶器”にもなってしまう。そんな厄介な相手のようです。
特に、青太文字でハイライトした部分は今お困りの”時間がない”につながる部分です。やはり完璧主義傾向があると、時間不足になりがちだということが表れていますよね。なんとかしたいものですね。
完璧主義を抜け出せない理由
ではなぜ完璧主義はやめたいと思っても簡単にやめられないのでしょうか。
それは、完璧主義が生まれつきの気質によるものだったり、育った環境が要因となって現れる性質だからです。
例えば、小さい頃から「ミスすると怒られた」「失敗体験で傷ついた」などが原因の場合、完璧主義は無意識に刷り込まれ、強い”心のクセ”となって残ってしまうので、大人になってから取り除くことが難しいです。
また、完璧主義だからこそうまく行ったなど、過去の成功体験があったり、完璧主義であることのメリットをより強く感じる場合もあります。
それだと尚更、完璧主義をやめようというインセンティブは働かないですよね。
例えば、人と話すことが大好きな人に『今日から一生誰とも雑談しないで生活してください』と言ってもなかなか難しいと思います。
それと同様に、完璧主義をやめたくても簡単にはやめられないのです。
成功する人や企業の特徴ー完了主義
 そんな厄介な完璧主義ですが、これと対になる言葉として「完了主義」というものがあります。あなたもこれまで『完璧主義から完了主義になることが大切!』と、何度か耳にしたことはあるのでは?
そんな厄介な完璧主義ですが、これと対になる言葉として「完了主義」というものがあります。あなたもこれまで『完璧主義から完了主義になることが大切!』と、何度か耳にしたことはあるのでは?
結論から言うと、実はこの完了主義は、成功する人や成功する企業が持っている大きな特徴のひとつです。順を追って詳しく解説していきますね。
完璧主義から完了主義に変わると手に入るもの
完了主義とは「完璧じゃなくても、まずはやり切ることに価値を置く考え方」です。
もちろん、「雑にやる」こととは違います。「完璧」を目指すのではなく、「今できるベストで一度区切る(=完了させる)」ことを優先するマインドですね。
では、完璧主義から完了主義に変わると、どんなメリットがあるのでしょうか?
得られるメリットを7つにまとめてみました。
1. 圧倒的な行動力
完璧を求めすぎると「まだ準備が…」と動けない。
でも「まず完了させよう」と決めれば、行動が早くなり、挑戦の数が増える。
2. 時間と心の余裕
細部までこだわり過ぎると、時間もエネルギーも消耗…。
完了主義は「80点でOK」にできるから、時間が生まれ、余白ができる。
3. スピード感のある成果
アウトプットの回数が増える=フィードバックが早く来る。
結果として、改善スピードも上がり、成果も早く出る。
4. 自己肯定感の回復
「できたこと」に目を向けられるから、
「また進めた」「今日もやれた」と達成感が積み重なり、自己肯定感が育つ。
5. チームワークの改善
自分の完璧さにこだわらなくなることで、
「人に任せる」ことができるようになり、人との連携がうまくいく。
6. 失敗への耐性がつく
完了主義は「とにかく出してみる」マインド。
だから失敗も「ネタ」や「学び」と捉えられるようになり、怖くなくなる。
7. 継続できる習慣が身につく
完璧じゃなくていいから「とにかくやる」が続けられる。
結果、継続力が身につき、積み上げができる。
いかがでしょうか。
”完了主義を意識すれば、早く切り上げられるから時間を生み出すことはできるだろう”
とだけ思っていた方は、完了主義に切り替えることが「時間を生む」以外にこんなにも多くのメリットがあるとお気づきでしたか?
そして実は、これらのメリットは、成功者が持つ多くの特徴と一致しているのです!
成功者の特徴は様々ありますが、その中でも例えば、これらの要素は全て完了主義が絡んできます。
- 行動の早さ(完璧よりスピード)
- 継続力(習慣化による積み上げ)
- 失敗を恐れない(PDCAを意識し失敗から学ぶ)
完了させ、量をこなすことで沢山失敗しながら学んでいく。また完了することで達成感と自己肯定感が生まれるから、継続に繋がりやすい。といった感じです。
”質より量”に関する実証実験
『量質転換の法則』という言葉を聞いたことのある方もいると思います。
これはドイツの哲学者ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(G.W.F. Hegel)が提唱した弁証法の三法則のひとつです。
簡単にいうと、ある「量的変化(少しずつの変化)」が、ある臨界点を超えると「質的変化(本質的な変化)」を引き起こすという法則ですが、これを発展させて、『スキルを磨く練習(量)を積み重ねることで、ある瞬間に「成果が出る・周りから評価される」という飛躍的な変化(質)が現れる。』という意味で使われる事があります。
これは、量をこなすと質が伴ってくることを意味して使われていますが、実際に、質より量が重要であることを示す研究がいくつもあります。
陶芸クラスの「量と質」実験(陶芸の壺の話)
こちらは、デイヴィッド・ベイルズ氏とテッド・オーランド氏による共著『アーティストのためのハンドブック―制作につきまとう不安との付き合い方(Art & Fear)』の中で紹介されている有名な実験です。
- 概要: ある陶芸のクラスで、教師が生徒を2つのグループに分けました。一方のグループは「量」で評価され、学期中に作ったポットの総重量で成績が決まった。もう一方のグループは「質」で評価され、学期中に完璧なポットを1つ作ることでA評価を得られた。
- 結果: 学期末に、最も質の高い作品はすべて「量」で評価されたグループから生まれた。「量」のグループは多くの作品を作る過程で試行錯誤を繰り返し、技術を向上させていった。一方、「質」のグループは完璧な作品を作ることに囚われ、実際にはほとんど作品を作ることができなかった。
- 示唆: 特に初期段階においては、完璧を目指すよりも多くの作品を生み出すことが、結果的に質の高い成果に繋がる可能性がある。
ブレインストーミングに関する研究
次に紹介するのは、テキサス大学アーリントン校のポール・パウルス教授らによる実験です。
- 概要: ブレインストーミングの際に、参加者に「量」を重視する指示、「質」を重視する指示、あるいはその両方を重視する指示を与え、アイデアの数と質を比較した。
- 結果: 「量」を重視する指示を受けたグループが、最も多くのアイデアを生み出し、かつ質の高いアイデアも多く含んでいたという結果が得られた。
- 示唆: 多くのアイデアを出すことを目標とすることで、固定観念にとらわれない斬新なアイデアが生まれやすくなり、結果的に質の高いアイデアに繋がる可能性がある。
熟達に関する過去研究の考察
教育者向け専門誌American Educator誌(2004年春号)掲載のダニエル・ウィニングハム氏による記事がBloom(1985)などの研究をもとに、熟達(質の向上)には膨大な練習(量)が不可欠であることをまとめて解説しています。
- 概要: 様々な分野における熟達者の研究を分析し、才能や知能と練習時間の関係を調査した。
- 結果: 多くの研究で、熟達には才能よりも長時間の練習が重要であることが示唆されている。特に、ある程度のレベルに達した後も練習を継続することが、更なる質の向上に不可欠であることが示されていた。
- 示唆: 完璧を目指すだけでなく、継続的な練習によって量を積み重ねることが、長期的な視点で見ると質の高い成果に繋がる。
これらの研究は、必ずしも常に「量」が「質」よりも重要だと主張しているわけではありません。しかし、特に学習や創造の初期段階においては、量をこなすことで基礎的なスキルを習得し、試行錯誤を通じて改善を重ねることが、最終的に質の高い成果を生み出すための重要なプロセスであることを示唆しています。
完璧主義に陥り動きが止まってしまうよりも、まずは量を意識して取り組むことで、思わぬ発見や成長に繋がる可能性が高いと教えてくれています。
完了主義スタイルの実例
さらに、よりイメージを持っていただけるように、完了主義を重視していた著名人や企業の例を、こちらのサイトから引用して紹介させていただきます。
スティーブ・ジョブズの事例
ジョブズは、完璧な製品を目指しつつも、適切なタイミングで製品をリリースすることの重要性を理解していました。彼は「完璧を待っていては、何も生み出せない」という考えを持っていました。
実践例: – 初代iPhoneは、多くの機能が不完全な状態でリリースされました。例えば、コピー&ペースト機能は後のアップデートで追加されました。 – しかし、革新的なユーザーインターフェースと主要機能の完成度の高さにより、市場に大きなインパクトを与えました。 – その後の継続的なアップデートとユーザーフィードバックにより、製品を進化させていきました。
学ぶべき点: – 核となる機能を高い完成度で仕上げ、それ以外は後のアップデートで改善する戦略 – 市場投入のタイミングと製品の完成度のバランスを取ることの重要性
マーク・ザッカーバーグの事例
ザッカーバーグは、「Done is better than perfect(完璧より終わらせることが大切)」という言葉で知られています。
実践例: – Facebookの初期バージョンは、ハーバード大学の学生のみを対象とした非常にシンプルなものでした。 – 機能を少しずつ追加し、ユーザーベースを徐々に拡大していきました。 – 常にユーザーフィードバックを基に迅速な改善を行い、進化を続けています。
学ぶべき点: – 小さく始めて、迅速に拡大していく戦略 – ユーザーフィードバックを積極的に取り入れ、継続的に改善する姿勢
身近な企業の事例
製造業:3Mの15%ルール
- 従業員に労働時間の15%を自由な研究開発に充てることを許可。
- 完璧な計画や承認プロセスを経ずに、アイデアを素早く形にすることを奨励。
食品産業:スターバックスの季節限定メニュー戦略
- 完璧な新メニューを開発するのではなく、短期間の季節限定メニューを頻繁に導入。
- 人気のあるメニューは定番化し、そうでないものは早々に撤退。
効果: – 新メニュー開発のリスク低減
– 顧客の興味喚起と来店頻度の向上
– 市場動向の素早い把握小売業:ザラ(ZARA)の迅速な商品サイクル
- 完璧な商品ラインナップを準備するのではなく、少量生産で素早く市場に投入し、反応を見ながら追加生産を行う。
- 店舗からの情報を基に、迅速に新デザインを開発し、投入。
自動車産業:テスラのソフトウェアアップデート戦略
- テスラは、完璧な状態で車を販売するのではなく、基本機能を備えた状態で販売し、その後ソフトウェアアップデートで機能を追加・改善。
- 自動運転機能など、ユーザーフィードバックを基に段階的に機能を向上させる。
効果: – 市場投入の早期化
– ユーザー体験の継続的な向上
– 開発コストの分散
時間がない人はまず完了主義のマインドから
 いかがでしたか?
いかがでしたか?
完了主義がもたらすメリット、もっと具体的に言えば、完了主義があなたの成果を引き出す理由、納得いただけたでしょうか。
今何か取り組んでいるタスクや学習があれば、そのアウトプットを徹底して完了主義で取り組むことで時間も生まれるし、成果につながるのです。
考え方のヒント
ただ、単純に時間だけが増えれば良いからと思って、時間管理のテクニックに走るのは失敗の元です。
実際、ポモドーロタイマー(25分間ワークした後5分休憩など時間を決めて取り組む)や、重要性や緊急性などから優先順位をつけて取り組む等のテクニックで時間管理して、上手くいかなかったご経験はありませんか?
それは、タスク完了までの見積もりの甘さもあるでしょうが、あなたの完璧主義気質が邪魔をしている可能性も大いにあります。
決めた時間やスケジュールを守ろうとするよりも、完璧主義が顔を出してしまっていつまで経っても終われないのです。
だからこそ、完了主義が”自分の成長のために必須だ”という強いマインドを先に持って取り組むことがテクニックだけを取り入れるより重要になります。
具体的な実践方法
最後に、完璧主義を乗り越えて完了主義になるための具体的な方法を3つ程ご紹介します。
タスクを細分化し達成度を見える化する
大きな目標やタスクを前にすると、完璧主義者はその完璧な完成形を想像し、圧倒されてしまいがちです。その結果、挑戦することすら諦めてしまいかねません。
完了主義になるには、まず、大きなタスクを、実行可能な小さなステップに分解します。
次に、各ステップに具体的な期限を設定し、完了したステップを記録したり、チェックリストで消し込んだりすることで、達成感を可視化します。
このように、小さな「完了」を積み重ねることで、全体としての進捗を実感し、モチベーションを維持する事ができます。
優先順位を明確にする
一般的にもよく知られていますが、自分の目指す目的(取り組む理由)に対して重要性と緊急性の観点から優先度を決めて取り組む方法です。重要性と緊急性の高いことから取り組むのがセオリー。ただ、重要性と緊急性が高いものは、難易度が高かったり、量が多かったりと、解決するハードルが高くなることも多いです。
そんな時には、手がとまって思考停止していることの方がもったいないので、まずすぐに取り掛かれることからでも完了させていきましょう。取り組むうちに元々取り組みたかったタスクに取り組むモチベーションが湧いてくる可能性もあります。
一旦60%〜80%の完成度でOKと決める
パレートの法則でも知られるように、多くの場合、80%の成果は20%の努力で達成できます。残りの20%の成果を追求するために、80%の時間を費やすのは、非効率的。割り切るのが完了主義への第一歩です。もし80%に達しないと感じても60%でもOK。とにかく完了させることを優先しましょう。
その後のフィードバックを大切にして、さらにブラッシュアップさせるよう取り組めばOKです。
他にも完璧主義から抜け出す考え方や方法はたくさんあると思います。
ただ、この記事ではそのノウハウをご説明するより、あくまでそれ以前の考え方(マインドセット)をしっかり自分の中にインストールしていただくことが目的なので、ご紹介はこのくらいにしますね。
時間管理のノウハウ自体はまたこのブログでも詳しくご紹介したいと思います。
まとめ
いかがでしたか?
今回の記事では、【成果が出る人はみな完了主義⁉︎】「完璧主義で時間がない」から抜け出す最後の処方箋と題して、
- 完了主義が時間を生み出すだけでなく、成果につながる重要な要素であること
- その考え方を先に持つことが、完了主義を取り入れるポイントであること
の2つをさまざまな研究データや事例も踏まえながら説明してみました。
これまでどれだけ完璧主義をやめたいと思っても挫折ばかりだったという方でも、
今ご自身が「時間がないことで本当に困っている」そして「自分の目指す理想のためにより成果を出したいと強く思っている」この2つが当てはまれば、完璧主義から完了主義へ変われる日が近いかもしれません。
これから完了主義を目指したい人の気づきになれば嬉しいです。